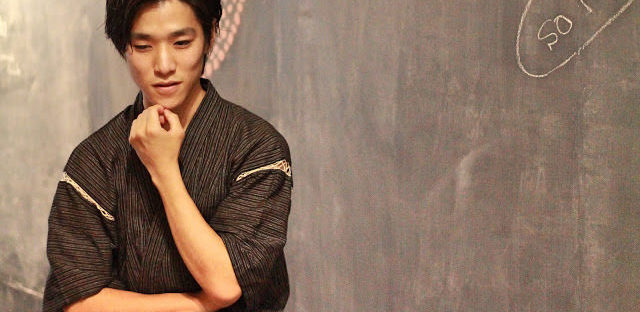そもそも、鍼灸ってよくわからないんです。
「鍼って痛いの?」
「お灸って熱いの?」
「本当に効くの?」
みなさん『鍼灸』という単語は聞いたことがあるのですが、『鍼灸』が何なのかは知りません。
でもそれは当たり前のことで、鍼灸師である僕ですら鍼灸を明確に説明できません。
なぜなら鍼灸の定義が人によって違うからです。
鍼灸師100人に「鍼灸って何ですか?」と質問したら100通りの答えが返ってくるでしょう。
それは鍼灸が目的を達成するための手段に過ぎないからです。
鍼灸師は「鍼を刺す人」ではなく「目的達成のために鍼とお灸を使うことが国から許されている人」だと僕は思います。
つまり、鍼灸師が掲げる目的が違えば鍼とお灸の使い方も違う。
実際に日本各地で行なわれている鍼灸治療を眺めてみると
・鍼の先端を皮膚に当てるだけ
・鍼は使わずにお灸だけを使う
・筋肉に深く鍼を刺す
・お灸をお腹の上で燃やす
・刺した鍼に電気を流す
目的によって様々な鍼灸治療が行われています。
もう少し視野を広げてみると、
鍼灸師が掲げる目標が違えば鍼とお灸を使わないこともあります。
鍼灸を受ける側のライフスタイルで大きく目標が変わるわけです。
「肩こり」という症状1つとっても
・札幌に住む主婦
・東京で働くデザイナー
・世界を飛び回る経営者
その人の立場や住む地域などで治療の目的、頻度、アドバイスの仕方が大きく変わりますよね。
「肩こり」という症状は、1つの結果に過ぎません。
大事なのは「肩こり」の背景にあるその人のストーリーやライフスタイルを理解することだと考えています。
そこで、東洋医学の持つ柔軟な考えが生きてきます。
陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる。
物事には変わり続けるものと変わらないものがある。
どんな症状であれ、その人の人生を丸ごと考えることができるのが鍼灸のいいところだと思います。
もし僕が体調を崩したら、病気だけを見る人よりも、人生を丸ごと親身になって考えてくれる人の治療を受けたいと思います。
そして鍼灸は日本の大切な文化であり、ビジネスです。
鍼灸を無形文化財として国が保護してくれたら嬉しいなと思うのですが、中々そうもいきません。
それなら、僕たちがきちんと仕事として残していく必要があります。
鍼灸の持つ様々な可能性を広げることが、僕たちの世代に託された使命だと感じています。